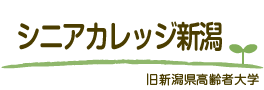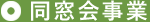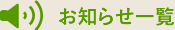「佐渡島の金山」が“世界の遺産”に
2024.9.9
今年度、基礎応用課程でご講義いただいた「佐渡を世界遺産にする新潟の会」専任講師の山田修さんより、学生の皆様へメッセージをいただきました。
(以下、原文のまま)
「佐渡の金山を世界遺産にしたい。講師として参加を」と佐渡出身の先輩に誘われたのはちょうど十年前。「~新潟の会」発足の間もなくだった。県内の小学校への出前授業が始まり、三年後には当シニアカレッジの講座も、と声がかかった。世界遺産登録までは長い道のりが待っていた。日本国内の世界遺産候補になったものの、かかりつけ医でいう〝中待合室〟に呼ばれてから何度も空振りが続いた。そのせいか世界遺産登録は「ようやく」という思いが強い。一過性ではなく持続可能な世界遺産に向けた受け入れ態勢の整備は急務だ。要点を整理したい。
●勧告の要はただひとつ
登録が決まったユネスコ総会(七月下旬、インド)を前に、諮問機関のイコモスが日本に対し勧告を行った。まだ課題が多いので「登録」ではなくそのひとつ下の「情報照会」。多分そうなるだろうと思っていた私の予想は的中した。勧告は追加分も含めて全部で十一項目あったが、要は「全体の歴史を現場レベルで包括的に扱う説明・展示戦略を策定し、施設・設備等を整えること」に絞られていた。「佐渡は世界遺産に値する」と勧告冒頭で示されていたからなおこの項目の存在が際立った。
●金山開発と朝鮮半島出身者
相川の金山関連施設ど真ん中にある相川郷土博物館に「朝鮮半島出身者を含む鉱山労働者の暮らし」コーナーが公開されたのは登録決定の翌日。その日の朝、「朝鮮出身者の展示不要だ」という新聞社説もあったから国、新潟県、佐渡市で早手回しをしていたのだろう。「韓国が同意。逆転登録」という社説もあり、登録実現に向け水面下での外交交渉がうかがえる。「佐渡金山の史実を伝えていきたい」(平成二十九年、佐渡市世界遺産推進課)という地元の思いを正面から受け止めたい。
●「流人」と「島流し」と「島送り」
佐渡は奈良時代から流人の島。鎌倉時代には上皇も流されている。また江戸時代までに200人超の罪人が遠島(島流し)に服している。罪はないのに都市に流入した若者が捕えられ、金山の水替え人足として働かされた歴史もある。そのせいか坑道を見学した後「罪人たちが暗闇の中で強制労働させられていた」と誤った認識を示す観光客もいる。罪人は金の採掘作業にはかかわっていない。誤認をどう伝えていくか。
●佐渡は「宝の島」。全島が「世界遺産」
トキが生き残ったほどの自然が残り、流人や幕府の直接支配、北前船寄港といった歴史の流れは佐渡独特の文化を育んだ。食の豊かさに加え、「世界農業遺産」と「日本ジオパーク」も後押しする。アースセレブレーション、トライアスロン等世界に顔を向けた階段も上ってきた。佐渡には金山を取り巻く懐の深さがある。島の存在そのものが世界遺産といってもいい、との思いをより強くしている。(令和6年9月記)
【山田講師】
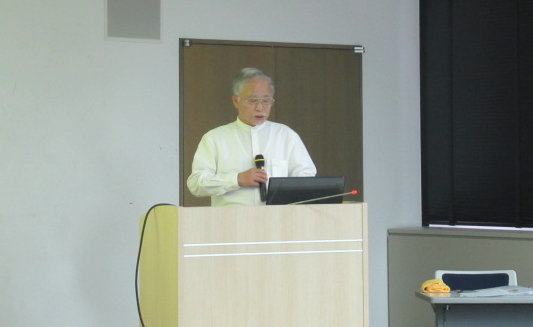
【講義の様子】
BSN「週刊 県政ナビ」にシニアカレッジ新潟が紹介されます
2024.3.5
3月10日(日)11:40~BSN(新潟放送)「週刊 県政ナビ」に、シニアカレッジ新潟が紹介されます。放送の内容は、『令和6年度学生募集』と『卒業生のその後』についてです。
ご出演いただいた卒業生は、令和2年度長岡クラス卒業の藤巻靖久さん。藤巻さんは、基礎応用課程(2年制)を受講され、卒業後は長岡クラスの運営協力員も務めてくださいました。カレッジを受講した感想や、現在「新潟歩く会」のメンバーとして、会員の皆さんとウォーキングを計画し活動されている様子が紹介されます。詳しくは、当日の放送をご覧ください。
※令和6年度の学生申込は3月15日(金)から始まります。週刊 県政ナビをご覧になり、関心をお持ちになった方は是非、お申し込みください(ホームページ「学生の募集・申込」フォームから申し込むことができます)。

【会のメンバーとトレーニングで歩くやすらぎ堤(新潟市)で、インタビューを受ける藤巻さん】
 【実際に歩いていただきました】
【実際に歩いていただきました】
- 2025.4.1
- 長岡市社会福祉協議会「社協ふくし塾」のご案内
- 2025.2.25
- シニアカレッジ新潟の令和7年度学生募集休止と今後について
- 2025.1.30
- 「同窓会事業」ページを更新しました
- 2025.1.7
- 「学生の活動」ページを更新しました
- 2024.10.16
- 「学生の活動」ページを更新しました